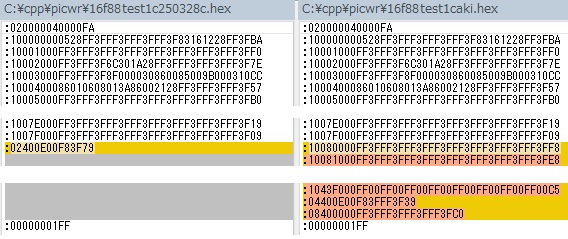logfile piciolog\0328183217.txt open
*** pic i/o ***
picio-30 connected
>/hload 16f88test1c.hex
loading 16f88test1c.hex ...
i=172,binbfend=68
>/picwr
400C[A9][50][36][91]
*******picwrend
>/verify
inbfend=0
400C[A9][50][36][91]
(01)(A9)(50)(36)(91)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)
(02)(05)(28)(36)(91)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)
(04)(83)(16)(12)(28)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)
(04)(6C)(30)(1A)(28)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)
(0C)(8F)(00)(00)(30)(86)(00)(85)(00)(9B)(00)(03)(10)(16)(9D)(51)(80)
(0A)(86)(01)(06)(08)(01)(3A)(86)(00)(21)(28)(03)(10)(16)(9D)(51)(80)
(10)(F8)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
vfend
error=0
>/picrdf 16f88test1c250328c.hex
400C[F8][3F][FF][3F]
type=04,uadrs=00
[08]
0000[10][05][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][83][16][12][28][FF][3F]
0010[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
0020[10][FF][3F][FF][3F][6C][30][1A][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
0030[10][FF][3F][FF][3F][8F][00][00][30][86][00][85][00][9B][00][03][10]
0040[10][86][01][06][08][01][3A][86][00][21][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
0050[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
07D0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
07E0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
07F0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]
[01]
type=04,uadrs=01
[08]
400E[F8][3F]
[10]
>/exit
|