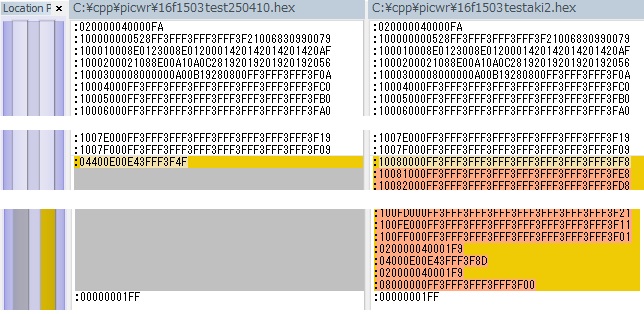>/hload 16f1503test.hex
loading 16f1503test.hex ...
i=225,binbfend=92
>/picwr
400E[FF][3F][FF][3F]
i=6,b=2,[04]0000
[05][04][02][00][00][00][00][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(01)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
i=12,b=2,[00]0000
[05][00][02][00][00][05][28][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(10)(01)(00)(02)(00)(00)(00)(00)(00)(02)(03)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
i=88,b=2,[00]000e
[05][00][02][00][0E][E4][3F][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(10)(03)(00)(02)(00)(0E)(01)(01)(00)(3A)(03)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
picwrend
>/verify
inbfend=0
400E[03][00][02][00]
i=6,b=2,[04]0000
[06][04][02][00][00][00][00][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(01)(03)(00)(02)(00)(0E)(01)(01)(00)(3A)(03)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
i=12,b=2,[00]0000
[06][00][02][00][00][05][28][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(02)(05)(28)(02)(00)(0E)(01)(01)(00)(3A)(03)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
[o][o]
i=88,b=2,[00]000e
[06][00][02][00][0E][E4][3F][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF][FF]
(10)(E4)(3F)(FF)(3F)(43)(33)(9D)(19)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)
[o][o]
vfend
error=0
>
|